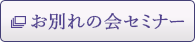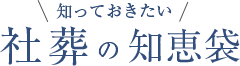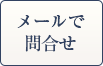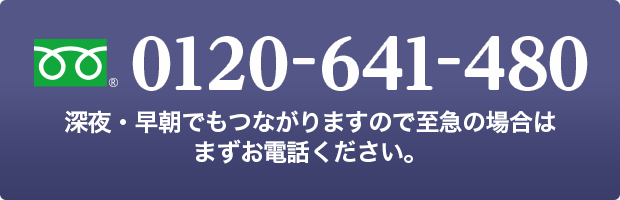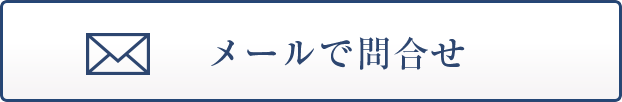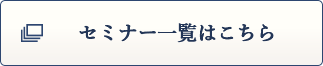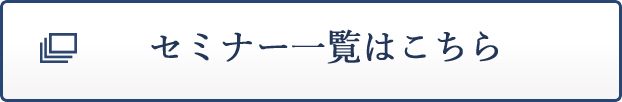お別れの会における献花について
無宗教式で執り行われる「お別れの会」での献花の作法についてご紹介します。

お別れの会は形式が自由
社葬対象者の死去に際し、企業がその故人を偲ぶために執り行う「社葬」。そのスタイルには宗教儀礼に則った形式のものから、宗教儀礼にこだわらず自由な形式で執り行うお別れの会と呼ばれるものなどがあります。
無宗教式のお別れの会ですが、途中、指名献花や一般献花、お別れの言葉などの式典が行われるケースと、式典はなく参列者は開式時間内に来場し順番に献花を行うケースがあります。式典はなくとも献花は行うことがほとんどのため、その作法を知っておくことが必要になります。
お別れの会における献花の流れや作法を事前に知っておき、当日慌てることなく、きちんと献花ができるようにしておきましょう。
知恵袋内の「お参りの仕方‐献花の作法」の記事でも触れていますが、ここではさらに掘り下げてご説明いたします。
献花は何のためにするのか
献花とは、主にキリスト教の葬儀において、参列者が献花台に白い花を捧げることを言います。仏教における焼香、神道における玉串奉奠(たまぐしほうてん)と同じような位置づけの、故人を供養するための儀式です。
もとはキリスト教式の葬儀で行われていたものでしたが、無宗教の葬儀や今ではお別れの会でも献花を行うことが一般的です。
無宗教の葬儀やお別れの会における献花の際には、白いカーネーションが多く用いられます。しかしながらカーネーションでなければならないという決まりはありません。ほかには白いバラやカラー、菊を用いることもあります。故人が好きだった花などが献花用の花に選ばれることもあります。
お別れの会における献花までの基本的な流れ
献花のための花は事前に会の主催者が準備していますので、自分で花を買って持って行く必要はありません。またホテルでのお別れの会では献花や会食の邪魔にならないよう、クロークに荷物を預けておくようにしましょう。
献花用の花は、献花の列に並び順番が近づいてきたときに、参列者一人一人にスタッフから手渡されます。流れ献花の場合には会場に席は設けられていないため、到着後は着席せずに献花の列に並び、その後会食の場へと進むのが一般的です。会食会場への動線上にお別れの会委員長や喪主の方がおられますので、そこで手短な挨拶をしましょう。
式典がある場合は席が設けられており、着席した状態で式次第が進みます。献花は順番が決まっており、一般的にはお別れの会委員長、喪主、ご遺族の順で進められ、指名献花に選ばれている方(指名献花者)がその後に続きます。指名献花者以外の参列者は、そのあとに一般献花として順次献花を行い、席には戻らずに会食があれば会食会場へ進みます。
自分の順番が来たら、以下の手順で献花をします。
① 案内に従い前方の献花台の方へ進みます。
② 献花台のそばでスタッフから花を受けとります。(両手で受け取るようにします)
③ 茎が左側に来るように花を横にして持ちます。右手で花を受け、左手は茎の上に沿えるような形です。
④ 式典がある場合は着席しているご遺族の方向へ一礼し、流れ献花の場合はそのまま進みます。
⑤ 祭壇の前に立ったら遺影に一礼し、花の根元が祭壇のほうに向くように花を捧げます。
⑥ 遺影に向かい再び一礼し、黙とうを捧げます。(合掌やお祈りなどは、そのお別れの会のスタイルに合わせて行ってください)
⑦ 黙とうが終わったら、再びご遺族がいらっしゃる場合にはそちらへ一礼をし、案内に従い進みます。お別れの会委員長や喪主がその先で立礼をしている場合にはそちらで挨拶をします。

お別れの会は、宗教儀式に則った社葬のように宗教儀礼は行いませんが献花というお参りの儀式は行われます。堅苦しい厳格な作法が要求されるわけではありませんが、故人を偲び送り出す儀式ですので、基本をおさえておきましょう。
公益社では社葬に参列する際のマナーやしきたりについてのご相談も承っておりますので、お別れの会に参列する予定のある方、または自社でお別れの会を開くという方はぜひ公益社の無料相談窓口をご活用ください。