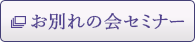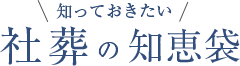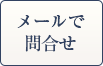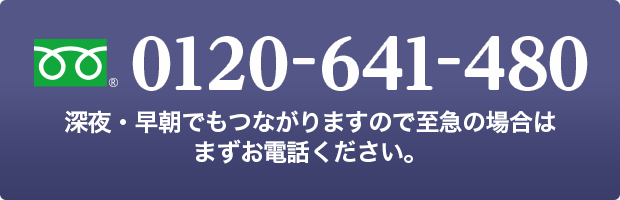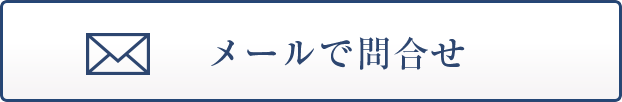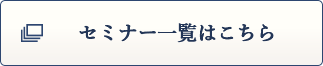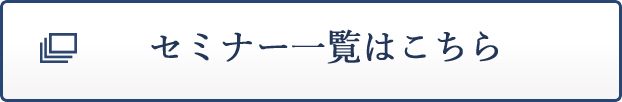「お別れの会」の香典に関して
お別れの会に参会する際に香典が必要なのか、また持参する場合の金額やマナーについてご説明します。

個人のお葬式には香典を包むのが一般的ですが、企業が主催する「お別れの会」では香典を受けるのでしょうか?またそれはどのように判別すればよいのでしょうか。
お別れの会は故人を追悼する場ですが、香典については辞退されるケースがほとんどです。まずは参会予定のお別れの会には香典が必要かどうかを確認しましょう。そして必要な場合には、マナーをふまえて持参するようにしましょう。
お別れの会に香典を包んで行くべきか
お別れの会で香典を受けているかどうかは、案内状や通知状を見るとわかります。
案内状に「香典辞退」の表記がある場合は、香典は持参しないようにします。
では香典を受ける場合にはどのように書いてあるかというと、香典についての表記はありません。香典についての「表記がない」場合は、「香典を受ける」ということを意味します。その場合は参会者がお別れの会当日に持参しましょう。通常最終的には企業を通じ遺族にお渡しされます。
なお、供花・供物を受けているかどうかについても案内状を見ればわかります。香典と同様に、案内状に辞退する旨の表記がなければ受けるということを意味します。
企業主催ではなく有志などによるお別れ会や偲ぶ会では、香典ではなく会費制の場合もあります。
お別れの会では香典は辞退であるケースがほとんどですが、従来お世話になっている方のお別れの会であれば、参列する以外にも弔意を示したいということもあるでしょう。その場合には弔電や供花を出しましょう。
香典を受けないということが分かる前に香典を預かってしまった場合や、有志による香典が集まってしまいお渡ししたいというケースもあるかもしれません。その場合は当日会場でお渡しするのではなく、相手企業の窓口(総務部や秘書室)を通じてその旨を伝え、後日あらためてご遺族に直接持参するのが丁寧な対応となります。なおお渡しする際に「有志からの気持ちですのでお返しは必要ありません」と一言添えると、ご遺族も負担に感じずにすみます。
香典を持参するときのマナー
お別れの会では持参する機会の少ない香典ですが、持参する際にはどのようなことに気を付ければよいのかをご案内します。
この場合の香典は、企業の代表者名で用意します。
個人葬と同様に不祝儀袋(香典袋)に封入し、袋は水引き(結び紐)が「結び切り」になっており、「のし」の付いていないものを選びましょう。表書きは仏式であれば「御香典」「御香奠(おこうでん)」「御霊前」など、キリスト教では「御花料」、神道では「御玉串料」や「御榊料(おさかきりょう)」、無宗教式の場合は「御供」「御香奠」などとします。薄墨を用いた毛筆書き(筆ペンも可)が正しい作法とされていますが、現代では濃墨でも問題ありません。
表書きや中袋には送り主の名前や住所は正確に丁寧に記載しましょう。所属企業や部署・役職なども書いておくと遺族が故人との関係を理解するのに役立ちます。
金額は、先方とのお付き合いの程度や故人の社会的地位によって1万円・3万円・5万円などと変わってきます。まずお別れの会(社葬)参列時の規定が設けられている場合はそれに従い、すでに自社内に過去の記録がある場合は慣例に従って判断しましょう。
当日は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、香典を手渡すときは、受付で表側を上にして袱紗を開き、表書きの名前を相手側から読めるように向けて差し出します。
お別れの会は、弔事の場であると同時に企業対企業の大切なお付き合いの場でもあります。参会者は会社を代表することになるので、事前にご案内事項をよく確認し、間違った対応をしないよう気を付けましょう。香典のほかにも、お別れの会における弔意表現には供花や弔電などがあります。それぞれのマナーについて不明な点がありましたらご案内いたしますので、どうぞお気軽に公益社にご相談ください。